荒磯会<あらいそかい>
「もう20年以上前になりますか、新富町の料亭松志満<まつしま>で父十一代目團十郎が一門の弟子達に勉強会をさせたのが始まりで、正式に第1回を名乗って致しましたのは昭和38年7月の砂防会館です。私は『勧進帳』を父に教わり初役で勤めまして、その後は女形もしなければと、『鏡獅子』の弥生では翠扇<すいせん>おばさんにすっかりお世話になって……」嬉しそうに大きな目で遠くを見て、海老蔵氏(現團十郎)が先日話してくれた。
発足時の趣旨は一応遂げたので荒磯会は昭和48年第7回をもって終る。実際は夏の公演なので、この頃歌舞伎教室などに出演することが多く、稽古期間が少なくなり、それでは初めの目的に反しますし、と亡きお父さんに似た誠実な言葉で御子息は結んだ。
荒磯模様<あらいそもよう>
 中国から渡来して茶入<ちゃいれ>等に珍重された数々の名物裂<めいぶつぎれ>の中に荒磯緞子<あらいそどんす>という逸品がある。 中国から渡来して茶入<ちゃいれ>等に珍重された数々の名物裂<めいぶつぎれ>の中に荒磯緞子<あらいそどんす>という逸品がある。
「荒磯」は日本名で、魚・波・岩の文様を指し、中国では「龍門の鯉魚」という吉祥文、これから引用した波頭に鯉の跳ねあがる勇壮な柄<がら>は、『極付幡随長兵衛<きわめつきばんずいちょうべえ>』の舞台でお目にかかる。
主人公が花川戸のわが家でくつろぐ衣裳は濃地に白抜きの荒磯模様。九代目團十郎の創始にかかるこの役らしい男の美を端的にあらわす。「荒磯会」の名もこれに由来している。
荒事<あらごと>
現人神<あらひとがみ>が生<あ>れて荒ぶる、即ち荒事だ。
江戸っ児が祈りの気持ちをこめてその大本山市川團十郎家を守り、誇りとした所以<ゆえん>で、今度の十二代目襲名に、あらためて我等東京人が持ちたい心意気でもある。
今から300年前の延宝元年、初代團十郎が『四天王稚立<してんのうおさなだち>』の坂田金時<さかたのきんとき>に14歳で扮した舞台の成果と好評とを以って荒事の始とする。
これは現在、中学生の年頃である。その点にも意味があり、後々まで荒事は、情熱、若さ、純粋、正義感、いつも少年の心を失ってはならぬとされている。又、父祖の地と思われる甲州武士の気骨もその根元にあるのだろう。上方の和事<わごと>に対し江戸の荒事と云われるが、歌舞伎十八番の主人公すべて、荒っぽいから荒事なのではない。
市川少女歌舞伎<いちかわしょうじょかぶき>
戦後すぐに、豊川(愛知県)辺りで出来た少女達による歌舞伎劇団であり、今後は知らず、明治・大正期に多かった女歌舞伎役者の最後である。
日本舞踊を習っていた女の子が市川升十郎の世話で昭和23年一座を設け、数年後市川宗家直門<じきもん>となり、市川の姓を名乗る。一時は明治座のような大劇場に出演、人気を博すが、時の流れと各自年齢変化による抵抗とで消える。
市川流<いちかわりゅう>
七代目團十郎は舞踊にも関心が強く、事実上この人を流祖とし、九代目が流れの基礎と方針とを固め、その長女の二代目翠扇に受けつがれる。後に姪にあたる市川紅梅が流儀と共に三代目翠扇の名を継ぐが、独身のまま逝き、当代海老蔵(現團十郎)が現在は宗家となり、その妹の二代目紅梅が実務面を補佐している。
一本隈<いっぽんぐま>
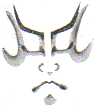 「国性爺<こくせんや>」の和藤内<わとうない>が典型。目張りの紅と、両こめかみから頬への半月状の紅筋とが、目尻の辺りでつながる。 「国性爺<こくせんや>」の和藤内<わとうない>が典型。目張りの紅と、両こめかみから頬への半月状の紅筋とが、目尻の辺りでつながる。
創生期の荒事には殆ど使われたというから、市川家の隈といっても良い。
外郎<ういろう>
「外<うい>」は唐の音<おん>であることからも判るように中国伝来の薬である。ちなみに新幹線で売りに来る名古屋名産は、この薬に形が似ているので名づけられ、後になってできた米の粉と砂糖とで作る蒸し菓子。
ここで説明したい品は、六百年前、中国元<げん>の人、陳宗敬が日本へ帰化、小田原で売り出した清涼剤である。「透頂香<とうちんこう>」という風雅な名も持っている。
効能をいいたてる見事な弁舌を真似て、二代目團十郎が『外郎売<ういろううり>』という役を『若緑勢曾我<わかみどりいきおいそが>』で演じ大当り、家の芸となる。この題名も巧いもので、小田原に縁ある曾我、爽やかな薬を若緑と称<たた>えたか。
魚河岸<うおがし>
「三箱」という言葉がある。
江戸で日に千両箱、今なら何億円だろうが、その値の金が落ちる三ヶ所、朝は日本橋魚河岸、昼は江戸三座の芝居、夜は吉原遊郭。
いずれも盛り場の代表でもあり、結びつきは固かった。
昔から「助六」上演の際には、魚河岸が鉢巻の紫ちりめんと下駄とを贈ったもので、助六が花道に出端<では>に「この鉢巻は」と頭を下げるのは、魚河岸への礼。今でも魚河岸後援会が役者の応援をしている。
江戸三座<えどさんざ>
江戸時代、官許の大劇場は四座ときめられていた。中村座、山村座、市村座、森田座。正徳4年に江島生島事件で山村座が取りつぶされ、あとは三座となる。支障があった時に控櫓<ひかえやぐら>といって、都座、桐座、河原崎座、この三座が代行する。九代目團十郎も、権之助と名乗って河原崎座の座元<ざもと>になった事がある。羽左衛門・勘弥、どれも本来座元の名。
江戸三幅対<えどさんぷくつい>
約200年前こういう言葉が街々に広まった。
当時の人気スター、五代目團十郎、力士の谷風、吉原の太夫花扇。
春好の絵には、五代目がこの二人の間で『暫』の扮装に軍配を構えた面白い図がある。
江戸根生<えどねおい>
「根生<ねおい>」は、本来「根つきの草木」をいうが、その土地に生まれ住みついている人々の事も指す。甲州か成田か、市川家の祖先は諸説あるけれども、團十郎を名乗った初代からは、はっきり江戸根生を看板にし、自分達もそのつもりだったろう。歌舞伎役者も数ある中、この言葉が一番ぴったりするのは市川宗家をおいて他にない。
初代も二代目も、上方へはるばる上ったが水にあわず、八代目、九代目もまた京大阪ではトラブルが生じ、どうも團十郎にとり江戸以外は鬼門のようで、江戸っ児はむしろそれを喜んだふしもある。
海老蔵<えびぞう>
この名は初代團十郎の幼名<ようみょう>で、名付親は父堀越重蔵の親友、侠客<きょうかく>の唐犬<とうけん>十右衛門とされている。
五代目團十郎が息子へ六代目を譲り改名する際に、口上で「親達は名人上手で江戸の飾り海老ですが、自分はザコで蝦蔵<えびぞう>を」と謙遜<けんそん>して、この字を使っていた。
いずれにしろ、市川宗家にとり、團十郎に次いで重い名である。
演劇改良会<えんげきかいりょうかい>
伊藤博文の女婿であった末松謙澄が中心となり、明治の新風潮に倣<なら>い演劇の旧弊打破を主眼として明治19年に設立された。メンバーには渋沢栄一なども入っている。主として「活歴<かつれき>」に凝り出した九代目團十郎をバックアップし『演劇改良意見』という本まで出版している。著者の末松の肩書きが凄いもので英国法学士技芸士と来る。花道やチョボを廃止、女優の登用等々、相当激しい議論もあるが、2、3年で立消えになる。
しかし、大阪に飛火した改良運動は新派の創立を呼び起こすような前向きの精神が、種々の新舞台を創りあげた。
大薩摩<おおざつま>
『矢の根<やのね>』の舞台で、大薩摩文太夫が、門礼者の姿で年始の挨拶に目出度い品々を持って来る。今は役者が扮しているが、昔は山台<やまだい>から太夫が本当に降りて来て、自分自身を演じたという。
江戸浄瑠璃の薩摩浄雲からこの名は出ているが、始祖は享保年間の大薩摩主膳太夫とされ、後に豪快な風<ふう>をそのまま長唄に吸収され、今も長唄連中で大薩摩某<なにがし>を名乗る人もいる。荒事は大薩摩がバックミュージックのミュージカルと言えぬ事もない。
大仏次郎<おさらぎじろう>
故十一代目團十郎を高く評価し、その資質を生かした新作を幾つも提供し、十一代目の大きな財産を築きあげた作家。
本名、野尻清彦。戯曲『若き日の信長』『江戸の夕映<ゆうばえ>』等。
晩年不治の病にかかられ入院中、唯ひとつ許された楽しみは病院に近い銀座のTホテルのバーへ行く事だったとか。そこの常連で席も定まっていて、私もよくお顔を見たが、亡くなる直前、殆ど飲まれぬグラスを手に知人と芝居の話しに花を咲かせ、帰りぎわ最後にふと、「團十郎が生きていてくれたら」と洩らされた声音<こわね>は、今も耳に残る。
※昭和60年1月発行 演劇出版社『演劇界増刊 市川團十郎』より転載。
編:藤巻透、イラスト:椙村嘉一
(昭和60年十二代團十郎襲名当時の記事ですので、若干時間を経てしまった内容もありますが、
極力当時のままの文章で載せさせていただきました。
転載をご快諾下さいました関係者の方々に、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。)
|



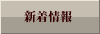

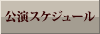

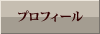
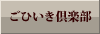

 中国から渡来して茶入<ちゃいれ>等に珍重された数々の名物裂<めいぶつぎれ>の中に荒磯緞子<あらいそどんす>という逸品がある。
中国から渡来して茶入<ちゃいれ>等に珍重された数々の名物裂<めいぶつぎれ>の中に荒磯緞子<あらいそどんす>という逸品がある。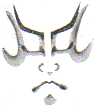 「国性爺<こくせんや>」の和藤内<わとうない>が典型。目張りの紅と、両こめかみから頬への半月状の紅筋とが、目尻の辺りでつながる。
「国性爺<こくせんや>」の和藤内<わとうない>が典型。目張りの紅と、両こめかみから頬への半月状の紅筋とが、目尻の辺りでつながる。